エネルギーマネジメントシステムISO50001要求事項とその対策(17)
ISO14001からISO50001で追加になった要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。このブログは、追加要求事項3: Cm(条項4.5.3)です。
• EnMS、En再確認、目標/計画を立案する際の立案/提案/決定ルートを全社に伝達し、意見を求めるルートを定めること。
• 現在社内にある意思決定ルートそのままで可。
次ブログへつづきます。
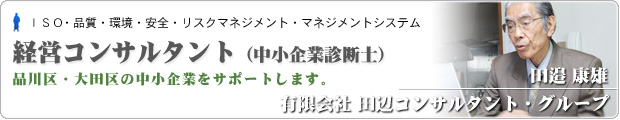
ISO14001からISO50001で追加になった要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。このブログは、追加要求事項3: Cm(条項4.5.3)です。
• EnMS、En再確認、目標/計画を立案する際の立案/提案/決定ルートを全社に伝達し、意見を求めるルートを定めること。
• 現在社内にある意思決定ルートそのままで可。
次ブログへつづきます。
追加要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。このブログは、追加要求事項3: Cm(条項4.5.3)です。
EnPとEnMSに関して内部Cmを行なうこと。全社員に方針実施/改善提案できるプロセスを確立/実施すること。外部Cmする場合は、そのプロセスを確立/実施すること。
Cm: コミニュケーション
次ブログへつづきます。
追加要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。このブログは、追加2 条項4.4.4対応策です。
• 工場内製造プロセス毎の原単位と世間の同様プロセス(複数)の原単位比較一覧表作成
• EnPIが古くなったり、プロセス改造があった場合は修正
• 修正手順書を作成する。
次ブログへつづきます。
前ブログからつづきます。
新技術開発センターから出版した「ISO31000活用マニアル」の概略内容は以下のとおりです。
全6章で構成されています。第一章から第四章までは、リスクマネジメントとISOの両者に関する基礎知識です。第五章が、ISO31000要求事項の解説であり、第六章がISO31000の活用方法です。
これら六章を「まえがき」「序章」「あとがき」で挟んであります。
次ブログにつづきます。
追加要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。
追加要求事項2: EnBL( 条項4.4.4)
EnBLを設定/維持/記録すること。以下の場合には、該BLを再調整すること。
―― EnPIが古くなって、Enの使用方法/使用量を反映しなくなった場合。
―― プロセスに大変化があった場合。
―― 再調整する場合が予め決めてある場合。
BL:ベースライン
EnPI:エネルギーパフォーマンス指標
次ブログにつづきます。
昨(2010)年9月以来、新技術開発センターにおいてリスクマネジメント国際規格ISO1000に関するセミナーの回を重ねてきました。該センターの御依頼をうけて今回、「ISO31000活用マニアル」を出版しました。従来のセミナーをまとめたものです。
御興味のある方は、以下を開いて見てください。
http://www.techno-con.co.jp/item/250151.html
なお、新技術開発センターのISO31000セミナーは、基礎編(規格解説)と応用編(活用法)に分けて今後も繰り返し開催します。第二回目は10/12(基礎)と10/26(応用)に開催されます。事前にこの本を購入してお読みになっておくと、セミナー内容がよく理解できます。
セミナーに御興味のある方は、以下を開いて見てください。
基礎編 http://www.techno-con.co.jp/item/17041.html
応用編 http://www.techno-con.co.jp/item/17042.html
次ブログ以降において本の内容の概略を紹介します。
追加要求事項とその対策を1条項ずつ説明しています。
追加1の条項4.4.3対応策
Enフロー図を描く
― 原料、燃料(化石/核)、電力に関する工場全体物質収支表
• 図に基づき工場内の主要En消費設備がどれであるかを確認する。
• 主要En消費プロセスを明確にする。― PFD、マテリアルバランス表、ヒートバランス表、電力バランス表
• プロセスの改善の余地を明確にする。
• 過去10年間の全消費量を経時変化図に描く。
• 大ユーザー消費プロセス毎の製品当たり原単位(原料、燃料、電力)を整理する。
• 社内研究開発会議の決定内容を整理する。それを踏まえて以下を整理する。
―― 主要En消費設備の技術開発優先順位
―― 技術開発した結果の原単位
―― 技術開発結果のEn消費設備の諸原を整理する。
諸原には、PFD、EFD、物質収支、En収支、オペレーション要員数/質を含む。
次ブログにつづきます。
追加要求事項とその対策を1条項ずつ説明します。
―― 追加要求事項1: En 再確認( 条項4.4.3 )
En再確認の手法/結果を構築/記録/維持/文書化すること。該構築においては、次の事項を行なうこと。 Enの使用方法/消費量を分析する。その分析は、以下のような測定等による。
―― 現在のEn源を確認する。
―― 過去と現在のEn使用設備/消費量を確認する。 Enの使用設備/使用量の分析に基づいて全使用状況を確認する。該確認は以下のように行なう。
―― EnPを分析/確認する。
―― 将来のEn使用方法/使用量を見積もる。改善機会を決定/順位付け/記録する。
―― 設備装置/システム/プロセス/要員等子を決定する。
次ブログにつづきます。
来る2011年12月10日(土)13:00~17:00、新技術開発センター主催により、第9回「生涯現役エンジニアになろう!!」セミナーを開催します。私田邉康雄が講師を引き受けます。場所:同センター研修室(メトロ半蔵門徒歩2分)、受講料:15,000円(税込)。これは弊社が実施する技術者研修のひとつです。
新技術開発センター(電話03-5276-9033)に直接申し込めます。しかし、新技術開発センターにとって新規顧客である場合は、私から紹介すると20%割引適用されます。これは元来、講師に対する紹介リベートですが、私田邉康雄はそれを受領することを潔し(いさぎよし)としないので、受講者様へ還元させていただくものです。割引御希望の方はメールを下さい。
―― このセミナーは、弊社の技術者研修「生涯現役エンジニアの道」の一環です。エンジニアに対する支援の一つとお考えください。
このセミナーの第一回を受講した人の中から有志が出現。そして請われました。「引き続いて指導してほしい」と。これを快諾した結果有志が代表幹事となって「生涯現役エンジニア塾」が誕生しました。現在約40名の塾生がいます。過去9回の塾を開催し、2011年9月23日(祝日)に第10回目が開催されます。
人生尽きるまで技術者として活躍し、もと在籍していた企業の後輩から「先生」と尊敬されて人生をまっとうする道などを教えます。
講師田邉康雄の連絡先は以下の通りです。
メール:tanabe-yasuo@tanabe-consul.jp
電話:03-3776-2495
FAX:03-5742-7695
★生涯現役エンジニアになろう!!(9回目)【12月10日(土)】13:00~17:00 於新技術開発センター(東京メトロ半蔵門駅徒歩2分)の続きを読む ≫
来る2011年11月15日(火)10:00~17:00、新技術開発センター主催により、第1回「エネルギーマネジメントシステムISO50001の追加分へ無駄ない対応を」セミナーを開催します。私田邉康雄が講師を引き受けます。場所:同センター研修室(メトロ半蔵門徒歩2分)、受講料:39,800円(税込)。これは弊社が実施する技術者研修のひとつです。
新技術開発センター(電話03-5276-9033)に直接申し込めます。しかし、新技術開発センターにとって新規顧客である場合は、私から紹介すると20%割引適用されます。これは元来、講師に対する紹介リベートですが、私田邉康雄はそれを受領することを潔し(いさぎよし)としないので、受講者様へ還元させていただくものです。割引御希望の方はメールを下さい。
―― このセミナーは、弊社の技術者研修「生涯現役エンジニアの道」の一環です。エンジニアに対する支援の一つとお考えください。
ISO50001への対応に関して私は、以下のように考えます。
1) 素材・エネルギー産業の大企業
私が長年勤務していた三菱化学のような総合化学会社はISO50001認証/登録する必要はないと考えます。従来やってきた活動をISO50001が求めるような形式で整理し直すだけでよい。そして整理した結果を自己宣言すればよいのです。認証/登録する必要はまったくなく、審査機関の審査を受ける必要は全くありません。
2) エネルギー多消費方中小企業
一方従来エネルギーマネジメントを意識してやっていない企業においては、ISO50001が要求するような活動を新たに実施するとよいでしょう。これによって全社的エネルギー効率が向上し、大きな省エネ効果をもたらし、大きなコストダウンが得られます。私が経験した範囲でいうと、プラスチック成型加工をしている従業員200名の中小企業においては、私が指導した活動を実施することによって年間1000万円の省エネコストダウンを達成しました。この場合もその事実を自己宣言すればよいのです。審査員に1000万円の指摘をしてもらおうと期待しても無理です。単なる適合性審査しか期待できません。
―― 今回の「エネルギーマネジメントシステムISO50001の追加分へ無駄ない対応を」セミナーは、個人技術者(エンジニア)に知恵を与えるものです。しかし個人技術者のためだけの知識ではありません。この知識を積みました技術者は、在職中に企業の高度先端技術開発等に対して大きな貢献ができます。即ち企業から喜ばれます。よって企業のための技術者研修です。
講師田邉康雄の連絡先は以下の通りです。
メール:tanabe-yasuo@tanabe-consul.jp
電話:03-3776-2495
FAX:03-5742-7695
★エネルギーマネジメントシステムISO50001の追加分へ無駄ない対応を(1回目)【11月15日(火)】10:00~17:00 於新技術開発センター(東京メトロ半蔵門駅徒歩1分)の続きを読む ≫
ISO50001に関するブログを書いています。最初に私のエネルギーマネジメン原点である京都大学工学部燃料化学科の紹介がすみましたから、いよいよISO50001要求事項とその対策に入ります。
―― ISO50001は、ISO14001に比較してエネルギーマネジメントが追加されています。条項数でいうと、ISO14001の18条項に対して7条項増加して26条項です。
―― 私は、ISO14001において独特のPDCA図を作成し、それを新技術開発センターから出版した「誰でもできるISO14001簡易環境影響評価法」において田辺式PDCA図を発表。これに対してISO50001PDCA図を今回作成しました。
―― 新たなPDCAにおいて、どこで増加したでしょうか。もちろん「P」と「D」です。Pにおいて3条項、そしてDにおいて4条項です。但し田辺式比較法によります。
次ブログにつづきます。
ISO50001に関するブログを書いています。最初に私のエネルギーマネジメン原点である京都大学工学部燃料化学科を紹介しました。その後で経験した三菱化学におけるエネルギーマネジメント経験は今ブログでは省略します。他のブログですでに紹介済みですから。以下は、前ブログからのつづきです。
―― ISO50001が2011年6月に発行されましたが、早くも認証/登録が始まったと報じられています。ISO認証/登録件数が低迷する中で、審査機関は絶好のビジネスチャンス到来と映るようです。
―― しかしよく考えてください。ISO50001は、企業のための規格であり、審査機関のための規格ではありません。
―― 素材・エネルギー産業においては、もともとエネルギーマネジメントを実施しています。私が定年まで勤務した三菱化学を例にとると、エネルギーマネジメントは日常業務として実施されていました。そして私は、33年間エネルギーマネジメントを担当していました。
―― その経験からして三菱化学等の素材・エネルギー企業は、法的/行政的要請対応以外ではISO50001認証取得をする必要がないと考えます。
次ブログにつづきます。
ISO50001に関するブログを書いています。要求事項はISO14001の19条項から7条項が追加になって26条項になりました。その追加条項はエネルギー特有のものですが、その対応策の立案は石油化学プラントの省エネ技術開発/省エネ設計/省エネプラント建設に携わってきた私にとって、極めて容易なものがありました。そこでそれを紹介しています。以下は、前ブログからのつづきです。
―― 私が卒業した京都大学工学部燃料化学科の歴史を説明しています。
私が在学していた昭和32~38年、工業化学科、燃料化学科、化学機械科、繊維化学科の4学科ありましたが、それが工業化学科に統合されて現在の定員数は235人であり、工学部の化学系学科としては、我が国最大数を誇ります。
―― 教室の開祖、喜多源逸先生が後進の育成に力を入れられた成果であり、学生数だけでなく研究の質も高く、ノーベル賞を二人輩出しています。福井謙一先生と野拠良治先生です。
―― 因みに、福井謙一先生から直接教えていただきましたし、野拠良治先生は同期生です。
―― 燃料化学科は、石油化学科、物質・エネルギー化学科と名前を変え、現在大学院の物質・エネルギー化学専攻にその系譜がつながります。
次ブログにつづきます。
ISO50001に関するブログを書いています。ISO14001の19条項から7条項が追加になって26条項になりました。その追加条項はエネルギー特有のものですが、石油化学プラントの省エネ技術開発/省エネ設計/省エネプラント建設に携わってきた私にとって、その理解は極めて容易なものがありました。そこでそれを紹介しています。以下は、前ブログからのつづきです。
―― そもそも大東亜戦争は、米国から石油の供給を止められたことに端を発していましたから、原油以外の原料からガソリンを合成することは国として喫緊の課題でした。
とくに緒戦の勝利で確保したスマトラ島の製油所からの輸送が、戦況の悪化にともなってままならぬ事態に陥った昭和18年以降においては国の存亡をかけた課題でした。
―― この課題を解決するために設立された学科が京都大学工学部燃料化学科であり、この課題に真正面から取り組んだ燃料化学科の福井健一先生は、自ら陸軍燃料廠勤務を志願され、技術将校となって陸軍燃料廠へ赴き、北海道滝川でプラントを建設してイソオクタン合成に専念されました。
―― この際に石油成分である様々な炭化水素の性状と様々な反応性に親しまれ、その御経験をベースにされて後に、実験しなくてもここの炭化水素の反応性を予測できる理論を開発されました。"フロンティア電子論"です。
これが評価されてノーベル賞を受賞されました。私も先生の御講義を受けた学生の一人として誇らしく思っています。"燃焼理論"と量子力学に基づいた"統計熱力学"であり、単位を取得させていただきました。
次ブログにつづきます。
ISO50001に関するブログを書いています。ISO14001の19条項から7条項が追加になって26条項になりました。その追加条項はエネルギー特有のものですが、石油化学プラントの省エネ技術開発/省エネ設計/省エネプラント建設に携わってきた私にとって、その理解は極めて容易なものがありました。そこでそれを紹介しています。以下は、前ブログからのつづきです。
―― 石炭をガス化/液化して合成/異性化した炭化水素と別途合成したイソオクタンを混ぜ、かつ、鉛化合物を添加してハイオクタンガソリンを造ったそうです。
―― 現在の自動車用レギュラーガソリンは、鉛など添加されていません。そしてオクタン価は90もあり、ハイオクガソリンのそれは96以上ですが、当時の戦闘機用ガソリンのオクタン価は87でしかなかったそうです。
―― 特攻機用のガソリンはこれであり、供給量が少ないので、訓練がままならず、出撃の際にやっとオクタン価87のガソリンがあてがわれたとのことです。これはNHKの番組"神風特別攻撃隊"で知りました。
次ブログにつづきます。