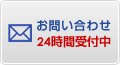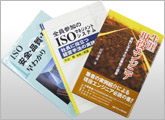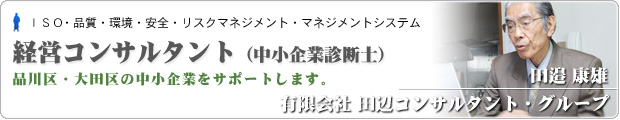書籍(本)「リスクマネジメントISO31000活用マニアル」を新技術開発センターから出版しました(6)
前ブログからつづきます。新技術開発センターから出版した「ISO31000活用マニアル」の概略内容は以下のとおりです。
―― 第二章のタイトルは「自然と共生してきたすばらしい日本人」であり、章内に立てた見出し以下のとおりです。
―― 見出し
「日本列島」「国民性」「リスクと共生」「自然崇拝」「大森貝塚と鹿島神社」「再生システム」「畏怖神・抱擁神」「外国のテレビ」
この第二章は、第一章の命題提起をうけてそれを展開するものです。漢詩"起""承""転""結"の承に当たります。ここに書いた見出しから内容を推定してください。
―― 御興味のある方は、以下を開いて見てください。
http://www.techno-con.co.jp/item/250151.html
―― なお、新技術開発センターのISO31000セミナーは、基礎編(規格解説)と応用編(活用法)に分けて今後も繰り返し開催します。第二回目は10/12(基礎)と10/26(応用)に開催されます。事前にこの本を購入してお読みになっておくと、セミナー内容がよく理解できます。
セミナーに御興味のある方は、以下を開いて見てください。
基礎編 http://www.techno-con.co.jp/item/17041.html応用編 http://www.techno-con.co.jp/item/17042.html
次ブログにつづきます。